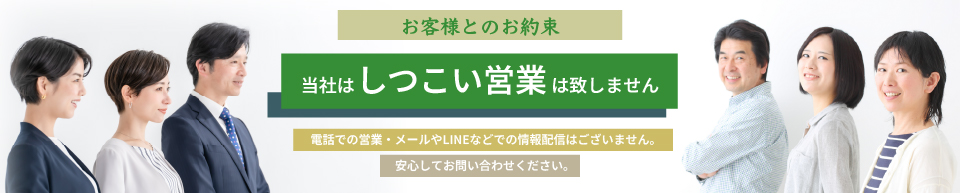- 2017年8月14日
- ブログ
- お盆休み
こんにちはリリーです。^^
お盆休みは地元に帰りました。(^^)/
車で帰る予定でしたが、毎年込んでいたのでたまには新幹線で帰ることに、だが、帰郷ラッシュで新幹線は混雑してました。
指定席は満席で自由席は座れず1時間半ぐらい渋々立つはめに…(´Д`) 座れない人は入口前に集まりただただ携帯をいじりながら時間を待つしかできない状況でした。( ̄д ̄)
午前9時頃で東京駅は物凄い人だったのでどこも混んでいたんではないでしょうか!!!
今日からUターンラッシュが始まるので昨日、一番遅い新幹線で東京に帰って座れたもののそれなりには混んでいましたね!('Д')
Uターンラッシュの方はお気を付けくださいませ。
ところでお盆の歴史と由来をみなさんご存知でしょうか?(迎え火・送り火・お供え物の意味)
お盆の墓参りや歴史と由来
お盆は仏教における盂蘭盆会(うらぼんえ)、または盂蘭盆(うらぼん)を略した言葉とされており、太陰暦(旧暦)では、7月15日(または8月15日)に行われる夏の御霊祭です。
現在では、お盆の期間は13日から16日までのところが多いようです。
仏教では、お釈迦様のお弟子様である目連様の母親が餓鬼道に落ちた時、お釈迦様の教えに従って多くの高僧たちに供養し、母を救ったことからはじめられたもので、仏様や先祖の恩に感謝し、お墓参りや迎え火などをする行事なのです。
また、お盆の歴史は古く、日本行われたのは、朝廷の時代で推古天皇(606年)十四年七月十五日斎会を設けたのが初めてとされ、斎明天皇(657年)三年七月十五日飛鳥寺で盂蘭盆会が催されたとあります。
その後、お盆行事は武家・貴族・僧侶・など宮廷の上層階級で主に催され、一般庶民に広まったのは江戸時代のようです。江戸時代に入ると庶民の間にも仏壇やお盆行事が普及し、又、ローソクが大量生産によって安価に入手できるようになってから提灯がお盆にも広く用いられるようになりました。
迎え盆(迎え火)・送り盆(送り火)
13日の夕方か夜に菩提寺とお墓に参り、祖先の霊を迎えます。
これを「精霊迎え」と言います。この時に霊が迷わず帰ってこられるように焚くのが「迎え火」です。地方によってはお墓からの道筋に、たくさんの松明かりを灯すところもあります。
そして、16日は送り盆です。この日に、お盆の間の一緒にすごした祖先の霊を送り出すことを「精霊送り」と言います。この時に「送り火」を焚くことも広くおこなわれています。

家のリフォームもそうですがお墓のリフォームがあるみたいです。

是非、この機会にご先祖様の為にお墓のリフォームを検討してみてはどうでしょうか?
家のリフォームをのことはリリーにお任せてください。
いつでもどこでもすぐに駆け付け致します。ww
お問い合わせこちら